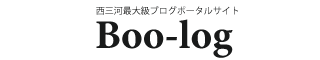いけばな展見て歩き
この一カ月、農村舞台アートプロジェクトの合間を縫って、
あいちトリエンナーレパートナーシップ事業「現代いけばなアート展」、池坊展、草月流愛知県支部展の三つに足を運んだ。
松坂屋の池坊展は
名古屋の歳時記のようなもの
いけばな人口が衰退するなかで一人勝ちの様相を呈しているのが池坊で、展覧会を囲むように京都の名店が門前市をなす光景はさすが。
東海地区は伊藤玉林、亀沢香雨など華道史に足跡を標した立華の名手を輩出した池坊王国で、こうした伝統の担い手として衆目の一致するのが特命派遣教授の柴田英雄。長谷川等伯の「松林図」を彷彿させる凛とした空間の支配力は他に比類がなく心地いい。
草月流愛知県支部展
「茜色に誘われて」
勅使河原蒼風、ニ代家元霞、三代家元宏と、伝統的ないけばなの世界にあって「表現としてのいけばな」の道を拓いた草月の創造のスピリットを継承することの至難さは想像に難くないが、草月に元気がないといけばなは面白くない。いわば草月の現在を確認することは「いけばなの定点観測」をするようなもので、楽しみ。
高島屋の正面を彩った四代家元勅使河原茜さんの大作
今回の草月展はJR高島屋の開店10周年を記念したもので
店内にはこんなお洒落なディスプレーも。
会場の入り口を演出したインスタレーションの部分。
草月を見る楽しみの一つは自由な気風にみちていること。
この作品も実作はアーチ状のインスタレーションで、
身体をつつむような浮遊感はさすが。
関連記事